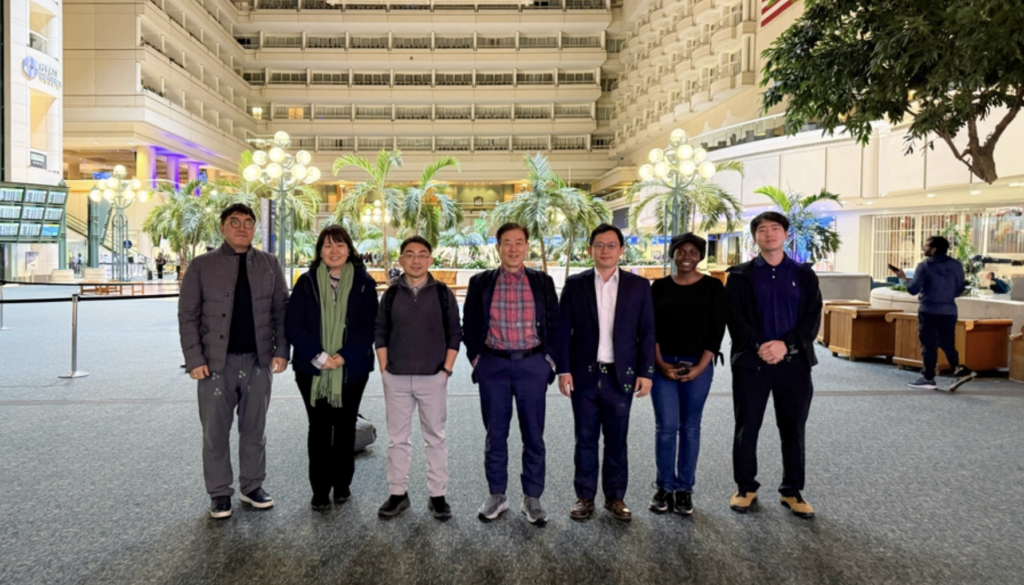
1. ピラトの人物像とイエス様への尋問の過程
ヨハネの福音書19章1節から16節に描かれるピラトとイエス様との出会いは、福音書全体の中でも非常に重要な分岐点です。この場面は表面的にはローマ帝国の総督であるピラトが、一人のユダヤ人であるイエスを尋問するプロセスですが、その奥には永遠の真理をめぐる対立が浮かび上がっています。そしてその対立の核心には、「神の子」であるイエス様が否定され、嘲られる姿があります。本文に登場するピラト、ユダヤの宗教指導者たち、そしてイエス様の態度を綿密に観察すると、最終的には神と人との間に結ばれた契約、そして神の子イエス・キリストが受けられる試練の決定的瞬間に立ち会うことになるのです。特に、張ダビデ牧師はこの本文を解釈する際、ピラトの内なる葛藤と、動じることなく従順の道を歩まれるイエス様の姿とが強い対比をなしている点を強調します。ピラトの心にも、わずかながらイエスを解放しようとする慈悲の念があったものの、結局は政治的圧力と自己保身の誘惑に屈してしまいました。一方、イエス様は「上から与えられていなかったならば、あなたはわたしに何の権限も持ち得なかったのだ」と宣言され、ご自身の死さえも神の主権下にあることを明らかにされます。
まずピラトは、イエス様に罪がないことを何度も確認しながらも、やむを得ずイエス様を鞭打ちにかけます。鞭打ちを行なった理由は、当時、被告に苛酷な体罰を加えることで訴えを起こした者たちの鬱憤や要求をやわらげ、処罰の強度を下げたり、あるいは解放する余地を作れるのではないかという期待があったからです。ルカの福音書23章16節と22節では、ピラトが「懲らしめて釈放する」と三度も繰り返して宣言している箇所がありますが、これが当時の慣習を示唆しています。ピラトはユダヤの指導者や群衆の前でイエスをとことん鞭打ちにかけたのち、「これほどまでに酷い姿にしたのだから、もうこの男を釈放してもよいではないか」と提案しようとしたのです。残酷な方法ではありますが、政治的な圧力にさらされていたピラトが最終的な妥協策として考えうる手段だったわけです。
しかしヨハネの福音書では、ピラトが鞭打ちの後にイエスを解放しようとしたという直接的な言及はあまり目立ちません。これは本文の焦点が、ピラトの寛容や個人的葛藤にあるのではなく、結局「十字架に引き渡されるイエス様」の運命と、その運命に加担する諸勢力の悪意に置かれているからだと考えられます。ヨハネは、他の福音書に出てくる「鞭打ってから釈放する」というピラトの言葉を省略することで、結果的にピラトもイエス様の死に決定的に加担した人物であることを際立たせます。罪のないことを知りながらも、自らの地位(総督職)と政治的安全を守るために無実のイエスを十字架刑に引き渡した責任を、ピラトは負うことになったのです。
では、ピラトはもともと残酷で無慈悲な人物だったのでしょうか。歴史家たちの記録によると、ローマの第5代ユダヤ総督として在任した彼(紀元26〜36年)は、ユダヤ人やサマリア人を何度も無慈悲に虐殺し、皇帝を神格化した軍旗をエルサレム神殿の近くに立てるなど宗教的侮辱とされる行為を行い、悪名を高めていました。彼はユダヤの伝統や民族感情を軽んじ、大小さまざまな対立が絶えなかった人物です。しかし、そんな人物であっても、イエス様と直接向き合った瞬間だけは、その無罪性と何らかの神秘性を直感的に感じ取ったのだと言えます。だからこそ「この人に罪を見いだせない」と繰り返し述べ、またイエス様が「神の子」であるという話を聞いたとき、いっそう恐れを抱いたのです(ヨハネ19:8)。
この段階でユダヤの指導者たちはむしろ「神の子」という宣言を聞き、さらに激しい憎悪と怒りに燃え上がります。ピラトは「もし本当に神の子であるならば、自分がむやみに死刑にするのは大きな罪になるのではないか?」と恐れを感じましたが、大祭司や指導者たちはその言葉に激昂してしまいます。ヨハネの福音書19章6節で、大祭司や下役たちが「十字架につけろ!」と叫ぶ姿は、血まみれのイエス様の姿を見ても微塵の同情すら持たないことを如実に物語っています。これは単なる政治的陰謀ではありません。張ダビデ牧師はこの場面を解釈するにあたり、「神の民」を自称してきた彼らの内に潜む霊的暗闇と無知が、どれほど深刻だったかを暴露するのだと強調します。ピラトのような異邦人の総督ですら真実を恐れ戦いていたのに、神の律法を知り、メシアを長く待ち望んでいたはずの大祭司や長老、律法学者たちは「我々にはカイサルのほかに王はない」という暴言さえ平然と口にするのです。
これは事実上、自らの信仰告白—「ただ神だけが私たちの王である」—を正面から否定するものでした。イスラエルのアイデンティティは『サムエル記』や『列王記』、さらには預言書全般にわたって、「神ご自身がイスラエルの王となられる」という土台の上に築かれています。それにもかかわらず、イエス様を殺すために、彼らはピラトに対して「この人を釈放するなら、あなたはカイサルの忠臣ではない」という脅し文句を投げつけるのです(ヨハネ19:12)。神への冒涜容疑を政治的な反逆罪にすり替え、ローマの権力にすがるという矛盾した態度を取るわけです。そして結局、ピラトもこの脅しに屈します。
最終的にピラトは「見よ、あなたたちの王だ」(ヨハネ19:14)と宣言し、イエス様をローマ帝国に対する反逆者として訴えるユダヤ人たちを逆に嘲ります。皮肉なことにこの言葉は、ピラトがある程度真実に近づいていたことを示唆します。イエス様が本当に王であることを、ピラト自身も朧げながら感じ取っていたかもしれません。しかしユダヤ人たちは「カイサルのほかにわたしたちには王がない」と声を張り上げ、自ら神の統治を否定する罪の奈落に陥っていきます。その劇的な瞬間、ヨハネの福音書19章16節は、ピラトが結局イエス様を十字架につけるために引き渡してしまったことを告げます。
このように、ピラトとイエス様の尋問の過程は、最終的に私たちに「真理とは何か?」という問いを投げかけます。ピラトが告白したように、「真理とは何か?」という懐疑に陥る人々もいれば、大祭司たちのようにそもそも真理に対する畏敬を失ってしまう人々もいます。ヨハネ18章37節でイエス様は「真理に属する者はわたしの声を聞く」と仰いますが、ユダヤの指導者たちはその声を拒みました。真理を切実に求め、へりくだって受け入れるよりも、自分たちの既得権や立場を最優先した結果、あらゆる正しい分別力を失ってしまったのです。信仰が深そうに見えるとか、熱心さが人一倍あるとか、そうしたこと自体が直ちに真理を追う証拠にはならないという事実が、この本文で明白になります。張ダビデ牧師は「熱意が即、真理追求の標識とは限らないことに常に警戒すべきだ」と強調します。大祭司や律法学者たちのように、自分たちは神の業をしていると確信しながら、実際には神の子を殺すという信じがたい罪悪に陥ることもあるからです。
イエス様が「どこの出身なのか?」と問うピラトの問いに沈黙されたこと、さらに「上から与えられていなかったならば、あなたはわたしを害する権限を持ち得なかった」と答えられた場面は、とりわけ重要です。イエス様はピラトの権威やユダヤ人たちの圧力によって死を迎えるのではなく、あくまで神のご計画と摂理のうちに従順してご自身を差し出されるのだということを強調されます。これは十字架へと至る道ですが、その道は決して敗北ではなく、永遠の勝利をもたらす道です。イエス様は必然的に死を迎えられなければなりませんでしたが、その死は贖いの死であり、全人類に救いの道を開く決定的な出来事でした。人の目には敗北のように見えても、張ダビデ牧師が幾度となく説教で語るように、「十字架は最大の勝利の現場」です。ピラトさえ恐れおののいたその惨たらしい死は、神の子どもたちを生かす命の道であり、死を滅ぼす勝利の道だったのです。
したがって、ピラトとイエス様の尋問は歴史のアイロニーであり、同時に霊的ドラマの頂点とも言えます。ピラトのように罪がないと知りつつもイエスを死に渡す者がおり、大祭司たちのように「カイサルのほかに王はいない」と宣言して神を捨てる者もいます。しかしその中にあってもイエス様は揺らぐことなく十字架の道を進まれます。これはある意味で「主の道を従う者」がいかに堅固に真理に立たなければならないかを問いかける場面です。真理に対して懐疑的なピラト、怒りで真理を拒むユダヤの指導者たちを見ながら、私たちは自分自身を省みる必要があります。自分の宗教的熱心が実は神の業に敵対する姿になっていないか、あるいは世の権力と妥協して真理を薄める行動を取っていないか、といった問いかけです。
一方で、ピラトがイエス様に「どこから来たのか?」と尋ねたとき、私たちはヨハネの福音書全体が提示するイエス様の正体性を思い起こす必要があります。つまり「上から来た方」、「この世に属していない方」、「父から来られた方」が、ヨハネが繰り返し描くイエス様の超越的なアイデンティティです。この壮大な真理をはっきりと理解できない限り、ピラトの疑問は解決せず、ユダヤ人たちの憎悪も解決しません。ただイエス様を「神の子」と信じ告白する信仰のうちに立つときだけ、真理とは何か、そしてなぜ主が十字架につけられねばならなかったのかを知ることができます。そしてこの信仰こそ、私たちに命と救いの道を開いてくれるのです。
ピラトは「あなたを釈放する権限も、十字架につける権限も私にはあるのだ」と豪語しましたが、実際イエス様はそれ以上の神の権威に依拠されていました。世の権威はピラトやユダヤの指導者たちのように揺らぎやすく、妥協しやすいものですが、イエス様が示された神の権威はむしろ沈黙と従順、そして自己を捨てることによって完成されます。これは世の常識からすると敗北に見えますが、霊的な目で見るなら、神の国の決定的勝利であり、罪と死を打ち破る絶対的力です。このように十字架へと向かわれるイエス様の姿は、私たちに神のご計画と主権を信頼させるものでもあります。
ヨハネの福音書19章1節から16節は、結局ピラトがイエスを十字架につけるように引き渡す場面で終わります。これは歴史的にも神学的にも深い意味を持つ出来事です。ローマ帝国の法廷で、その法を最も熟知していたはずのピラトが政治的圧迫に屈し、無罪のイエス様を死刑へと引き渡しました。そしてそのイエス様の処刑に最も積極的に協力したのは、皮肉にも神の選民だと自負していたユダヤ人の指導者たちでした。この矛盾だらけの歴史は、人間がいかに簡単に罪や自己保身の本能に屈し、妥協してしまうかを端的に示すものです。一方で、イエス様はどんな暴力や憎しみにも揺さぶられず、「上から与えられていなければ、何もできない」というお言葉の通り、ひたすら神の御旨のうちにあって、あらゆる侮辱と苦痛を受け入れられます。
張ダビデ牧師は、これこそ真の信仰の姿だと説きます。つまり、世の権力やプレッシャー、そして自分の命さえも父なる神の主権に委ね、揺らぐことなく従順する姿がイエス様の生涯と死に最も際立って現れているということです。そしてそれこそが私たちにも求められる弟子道(デサイプルシップ)の本質であり、ピラトとイエス様、そしてユダヤの指導者たちの対立は、単なる過去の歴史ではなく、現代の私たちにも直接的な挑戦を投げかけるものなのです。
2. 十字架の道と真の王であるキリストの意味
前述のピラトとイエス様の尋問過程を通じて、私たちはイエス様の十字架の出来事が単なる政治的陰謀や司法上の誤審に終わる話ではなく、神の救済計画の中で必然的に起こるべき出来事だったということを見いだします。十字架は、イエス様が選べた数ある死の形の中でも最悪の死でした。石打ちの刑で死ぬ可能性もあり、公権力の誤判によって牢獄で処刑されることも想像できたでしょう。けれどもイエス様は最も苛酷な苦痛と最大の恥辱を伴う十字架を「自発的に」負われました。これはヨハネ3章14節で「モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない」と仰せられた通り、人の子が「上げられる(高く掲げられる)」という救いの象徴が十字架だったからです。
十字架刑は古代ローマで最も凶悪な犯罪者に適用された処刑方式で、イエス様の時代のユダヤ人たちにとってはさらに「呪い」の意味合いが強いものでした。申命記21章23節に「木にかけられた者は神に呪われた者である」とあるため、彼らは十字架刑を神への冒涜に等しいものと見なし、恐怖し嫌悪しました。しかしイエス様はその呪われた者の位置にご自身で降りて行かれることで、むしろ全人類が負うべき呪いをその肩に背負われるのです。そこには、神の独り子であるイエス様がなぜ「しもべのかたちをとり、人間の姿をもって現れたのか」(ピリピ2:7)という根本的な答えが含まれています。このようにしてご自身を空しくし、死に至るまで従順されたイエス様の歩みが、神の国の価値を実現する道なのです。世の国では理解されがたい、また受け入れられにくい方法ですが、神の国の秩序は「仕えること、自己犠牲、従順」で要約できるのだといえます。
張ダビデ牧師は、この十字架こそが神の国が動く原理、すなわち「愛と犠牲、そして従順の中心」であると強調します。私たちが一般にイメージする「王」とは、王座に座って支配し命令を下す存在ですが、イエス様の王であることの完成形は、むしろ十字架につけられ死ぬことによって顕されます。これはヘーゲル流の正反合の逆説ではなく、そもそもイエス様が宣べ伝えられた神の国の価値観自体が「ご自身を低くする」ことにあるのだという預表でもあります。イエス様が弟子たちに「あなたがたの中で偉くなりたい者は仕える者になり、いちばん上になりたい者はみなのしもべとなりなさい」と仰ったのも、同じ文脈です(マタイ20:26-27)。
それゆえ、ピラトが「見よ、あなたがたの王だ!」と叫んだとき、イエス様は血にまみれた惨めな姿で立っておられましたが、霊的な意味ではそこが真の王座のような場所でした。なぜならイエス様こそが神の子、すなわち万王の王だからです。ユダヤの指導者たちはこれを嘲りの言葉として受け取り、ピラト自身も皮肉をこめて使ったかもしれません。しかし福音書は、この言葉が実は真実を宣言していると逆説的に示します。イエス様が十字架につけられたとき、その頭の上には「ユダヤ人の王」と書かれた札が掲げられました(ヨハネ19:19)。これはローマ法によって犯罪事実を掲示する名札でしたが、皮肉にもイエス様の本当の身分を宣言する称号となったのです。
この「王」であるイエス様を私たちはどのように理解し、どのように従うべきでしょうか。十字架の本質を正しくつかめないと、イエス様を誤解する可能性があります。単に「力の王、奇跡の王」としてキリストをとらえるならば、自分の生活に利益をもたらす道具あるいは神的存在としてのみイエス様を扱うことになりかねません。しかしイエス様が実際に示された王権は、死に至るまでの従順によって、すべての人を生かす犠牲の道でした。それゆえ、十字架は信じる者にとっては神の力ですが、信じない者には愚かしく見え、華々しさとは無縁に映るのです(コリント第一1:18)。
張ダビデ牧師はイエス様が受けられた二重の苦難—鞭打ちと十字架—を通して、私たちが覚えるべきことは、信仰の歩みが決して容易ではないことを示している点だと言います。「死に至るほどの苦難」という言葉の通り、イエス様は鞭によって肉が裂かれるほど打たれ、茨の冠で頭を刺され血を流し、最後には十字架に釘付けにされました。これは人類史上でもっとも残酷な処刑方式の一つです。ですが、その道こそが命へと向かう道でした。イエス様に従うとき、私たちの信仰生活にも時に大きな試練や迫害があるかもしれませんが、それは決して敗北ではなく、神が私たちを通して霊的な実を結ぼうとしておられる過程なのです。ヨハネ12章24節でイエス様が「一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一粒のままだが、死ねば多くの実を結ぶ」と仰った通りです。
このように十字架の道がどのようなものかを黙想するとき、私たちは自然に「弟子道の道」を思い起こします。主の生涯がそのまま私たちの手本となり、主の死がそのまま私たちの模範ともなるからです。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負ってわたしに従って来なさい」(マタイ16:24)という御言葉は、イエス様がたどられたその道を、私たちもともに歩むよう招いています。ところが実際、ピラトや大祭司、群衆たちの姿は、十字架の道がいかに私たち人間の本性と衝突するかを赤裸々に示しています。人は自分の利益、メンツ、権力を守るため、必死で十字架を回避したり、より大きな暴力で十字架にかけられたイエス様を排除しようとするのです。
結局、十字架は私たちが罪人であることを悟らせるだけでなく、神の愛がいかに大きく広大であるか、そして同時に私たちに何を要求するのかを明確に示します。「私も主のように十字架の道を歩めるのか?」という問いは、私たちの信仰を深い悩みへと導きます。張ダビデ牧師は「十字架の霊性を、単なる感傷や涙の訴えだけで終わらせず、生活の実際的応用にまで引き下ろす必要がある」と強調します。つまり、教会の中で口先だけ「十字架」を唱えたり、その象徴性だけを抱きしめるのではなく、実際の日常のさまざまな状況で自己否定と従順、そして犠牲の姿勢を実践しなければならないのです。
あるいは、私たちは十字架がもたらす「死」という言葉に本能的な恐れを抱くかもしれません。ピラトもイエス様が「神の子」だという話を聞いて恐怖を感じましたが、それと同じように私たちも真理の前に自分自身を直視するとき、恐れに襲われることがあります。「私は本当に神の前に正しく立っているのか? あのユダヤ人指導者たちやピラトのように、罪のない主を遠ざけ、世の権力に妥協していないか?」という自覚が生まれるかもしれません。しかしその恐れを越えて、イエス様が示された道を信仰によって見上げるなら、私たちが得るものは解放と自由です。罪悪感に縛られて生きるのではなく、イエス様の十字架の死と復活の中で「すでに私は罪赦されたのだ」と気づき、新しい命へと生きる道が開かれるからです。
十字架に向き合う私たちの態度は、どう変わるべきでしょうか。
第一に、ピラトのように真理を目の前にしながらも、政治的な計算や現実の損得を優先する態度を警戒しなければなりません。ピラトは本心ではイエス様を釈放したかったものの、民衆の声と「カイサルの忠臣ではない」という脅しに屈服しました。その結果、彼は永遠にイエス様を死刑に引き渡した責任者として歴史に名を刻むことになったのです。私たちも社会との衝突や個人的損害を恐れるあまり、時に福音を妥協したり、真理をねじ曲げる行動をとっていないか振り返ってみる必要があります。もしそうしているなら、無実のイエス様を引き渡したピラトと本質的には変わりません。
第二に、ユダヤの指導者たちのように、宗教的熱心が神の御旨に最も反する行動に結びつきかねないことを自覚する必要があります。彼らは自らが正統性を持ち、律法を厳守し、メシアを本気で待望していると自負していました。しかし実際のメシアであるイエス様がおいでになると、逆にその方を十字架にかけて殺せとピラトに差し出すことに率先したのです。あれほど待ち望んでいたはずの「神の子」を排斥するという矛盾に陥りました。信仰の熱心さが増すほど、私たちは常に御言葉と御霊のうちに正しい分別力を求める必要があります。さもなければ、盲目的な熱情が異端的で偏狭な道へと逸れてしまいかねません。
第三に、イエス様の十字架がただの宗教的シンボルではなく、私たちの生活における実体的な力であることを思い起こさねばなりません。イエス様が歩まれた道は、最後まで父の御旨に従う道でした。ゲッセマネの園で「アッバ、父よ」と叫びながら、自ら死の杯を拒まずに飲み干すと決断されたのは、愛なる父に結ばれた子としての信頼に基づいています。そしてその結果が、もっとも恐ろしい処刑方法である十字架でした。しかしそれは同時に、復活と命の入り口でもありました。イエス様の道を心から従い、強制ではなく喜びをもって従うためには、父なる神の真実を絶対的に信頼する必要があります。この信頼がないなら、十字架に参与することは単なる「自己苦行」や「不可能な理想」にしか残らないでしょう。
第四に、イエス様の死は「最も悲惨な姿」でありながら、同時に「最も栄光ある勝利」であるという事実をしっかり捉えるべきです。十字架はすべての霊的世界が転覆するパラダイム転換の場です。サタンはイエス様を十字架につけてしまえば自分たちの勝利だと考えました。しかしイエス様が死なれることで、すべての人の罪の代価が支払われ、むしろサタンが握っていた「死の権威」が破壊されます。イエス様の復活は十字架によって可能となり、その十字架によって救いの道が開かれました。私たちが信じ仕える王は、人間的な王座で豪華に支配する方ではなく、十字架で万民のためにご自身を捧げられた方なのです。
第五に、十字架は個人的救いにとどまらず、共同体的次元でも変化をもたらします。初代教会がイエス様の復活後、ローマ帝国の圧制やユダヤ人指導者の弾圧の中にあっても揺らぐことなく福音を伝えられたのは、この十字架の意味を深く自分たちのものとしていたからです。彼らは「主がすでに最も苛酷な道を喜んで進まれ、ついに復活されたのだから、どんな患難や迫害にも落胆しない」と告白しました。この告白が教会を一つにし、迫害の中でもかえって成長へと導いたのです。
最後に、現代を生きる私たちにも同じメッセージが与えられています。現代社会はイエス様の時代とは異なる文化や技術、制度を備えていますが、人間の内面に潜む罪性や世の価値観はさほど変わっていません。私たちは依然としてピラトのように政治的利益と真理の間で葛藤し、ユダヤの指導者たちのように宗教的熱心でキリストの本質を踏みにじることがあり、また群衆のように単純に世間の空気に流されて無実の人を責め立てることもあります。このような混沌と葛藤のただ中で、十字架はなおも私たちに道を示してくれます。それは真の王であるイエス様を仰ぎ見つつ、従順と犠牲へと進む道です。
張ダビデ牧師は、十字架神学を通して「教会が世の中で光と塩となるためには、まず十字架の前で自らを徹底的に低くし、悔い改めねばならない」と強く語ります。もし教会が世俗の権力や社会文化と結託してピラトやユダヤの指導者たちのようにイエス様を放置したり拒否したりするなら、それは十字架の精神を裏切ることです。教会が真の影響力を発揮するためには、第一に「ご自身を空にされたキリスト」に倣わなければなりません。第二に世の権勢を恐れるのではなく、「天の権威」に対する畏敬の念を持たなければなりません。そして第三に、いつも御言葉と祈りのうちに真理をわきまえつつ、互いに愛し合う共同体の中で十字架の霊性を実践するのです。
結局、ヨハネの福音書19章1節から16節に描かれるピラトの尋問シーンは、イエス様が十字架へと引き渡される過程を詳細に示すと同時に、私たちの信仰における最も重要な問い—「私はいったい誰を王としてお迎えしているのか?」—を投げかけます。大祭司や律法学者たちは口先では「神」を王と呼んでいたかもしれませんが、実際には「カイサルのほかに王はいない」と言ってイエス様を追い出しました。ピラトは表向きにはローマ皇帝に忠誠を誓う姿を見せましたが、実は自分の生存と保身のためにイエス様を十字架に追いやりました。彼らはいずれも、自称「王」であるイエス様を否定したのです。ですがイエス様は十字架を通して、まことの王であること—すなわちすべての人を救ってくださる神の支配者であること—を示されました。
十字架は完全な愛、完全な犠牲、そして完全な従順の集約点です。クリスチャンになるとは、この十字架の道を認め、それを自らの生活に受け入れることです。私たちの熱意がどれほど強くても、それが十字架の精神と食い違うならば、結局は大祭司たちのような歪んだ宗教的憎悪を再現するだけです。逆に世の権勢がいかに強大に見えても、十字架が示した神の権能と愛を体験するなら、私たちはピラトのように揺さぶられず、恐怖を乗り越えることができます。
したがって、ピラトの尋問過程を通じて明らかになるイエス様の十字架への歩みは、私たちに信仰と従順、そして犠牲の価値をあらためて思い起こさせます。神が私たちに与えてくださった救いの恵みはただで受け取ったものである一方、それはイエス様が莫大な犠牲によってもたらしてくださったものでもあります。私たちはこの真理を深く黙想しつつ、信仰の名のもとに他者を安易に裁いたり、暴力を正当化したりしないよう、自らを点検すべきです。同時に、どんな状況にあっても「真理に属する者はわたしの声を聞く」という主の言葉に耳を傾け、この時代を見極めながら神の御心にかなう生き方をせねばなりません。
今日でもキリスト教信仰が嘲笑され、一部の地域では激しい迫害が続いています。また、ある人々はイエス・キリストの福音を政治的に歪曲し、敵対勢力として扱うこともありますし、逆に宗教という名を借りて互いを攻撃する様子も見られます。このような混乱の中で、私たちが再びつかむべき中心は「十字架のイエス様」です。十字架上でイエス様は、罪のない方であったにもかかわらず、侮辱と苦痛をその身に負いながら、神の救いのご計画を完成されました。これこそが真の栄光であり、真の王としての力が示された瞬間なのです。
そして、この十字架の死を私たちが信じて従うとき、「復活の希望」が私たちの内に生きます。イエス様が十字架で終わったのではなく、復活されて死に打ち勝たれたがゆえに、十字架は敗北ではなく勝利となります。張ダビデ牧師は繰り返しこの点を強調し、「死に対抗する復活の生命力がなければ、十字架はただの過酷な刑罰譚で終わってしまう」と述べます。復活は十字架を正当化する言い訳ではなく、十字架の持つ愛と犠牲の意味が本物であることを証明する完成なのです。
結局、私たちはイエス様の歩みを通して「王」の定義を新たに学ぶことになります。世は力と制圧、武力によって支配する王を求めましたが、イエス様は愛と仕え、自己犠牲によって王であることを明らかにされました。そして私たちにもその道を歩むよう招かれます。ピラトの尋問や大祭司たちの裏切り、群衆の声にも動じることなく、最後まで十字架を選ばれたイエス様を黙想するとき、私たちはクリスチャンとしてのアイデンティティが何なのかを改めて自覚するのです。それは「神の子」イエス様と共に死に、共に生き、この地上で「神の支配」を証しすることにほかなりません。
もし私たちの生き方が、世の権力者や宗教指導者たちのように、自分の欲やプライド、政治的安全や宗教的独善に縛られているのなら、いくらでもイエス様を再び十字架につける罪を犯しうるでしょう。しかし十字架の道が狭く困難そうに見えても、その道が真の命の道であると信じて歩むとき、私たちは初めて神の子どもとして世に仕え、それを変革する力を体験することができます。その道に恐れがないとは言えませんが、イエス様がすでに歩まれ、復活によって完成された道であるという事実が私たちに勇気と確信を与えます。
ヨハネの福音書19章1節から16節に描かれるこの尋問事件は、表面上はユダヤ宗教指導者とローマの権力者との単なる政治的な結託や司法的不正の象徴のようにも見えます。しかし信仰の目で見るなら、それは人類を罪から救うための神の贖いの物語が最高潮に達する場面です。罪と不正が荒れ狂うただ中で、イエス様はご自分を最後まで差し出して「死に至るまで従順」され(ピリピ2:8)、私たちはその従順によって救いを得ました。これこそ福音であり、私たちが望みを置くメッセージなのです。
結論として、ピラトとユダヤの指導者たちの悪しき姿、そしてイエス様の苦難を対比させて眺めるとき、私たちは三つの教訓を得ます。
第一に、真理を知らなければなりません。真理を知らないままでは、宗教的熱心であろうと政治的権力であろうと、そこには希望がなく、結局罪のない者に最も酷い暴力を加える危険性をはらんでいます。
第二に、十字架の道を回避してはなりません。十字架は苦難と犠牲を意味しますが、同時にそこが復活の栄光へとつながる唯一の道であることを覚えるべきです。
第三に、「神の子」であるイエス様の正体を単なる教義として暗記するのではなく、私たちの生活の中で日々体現すべきです。イエス様を「王」として認めるなら、私たちのあらゆる決定や言動がその王の統治にふさわしいものへと変えられていくはずです。
張ダビデ牧師はこの箇所で、「真理を握りしめ、十字架に従う者だけが、真の教会を形づくることができる」と力説します。教会が世のただ中でイエス様の十字架の愛を体現する共同体となるためには、自己中心的な宗教や世俗的権力とは決して両立しえません。教会はいつも十字架で殺されたイエス様を見上げ、その方が復活を通して告げられた新しい命の約束をしっかりと握るべきです。これこそ主の弟子として歩む道であり、真に福音の力が示されるところです。
このようにヨハネ19章1節から16節まで続くピラトの尋問場面と、イエス様が最終的に十字架刑を言い渡されるプロセスを深く黙想するなら、一方では私たちの内なる「ピラト的要素」や「大祭司的要素」、「群衆的要素」に気づかされるかもしれません。しかし同時に、そうした罪人に向けてご自身の命をささげてまで救いを施されるイエス様の限りない愛と従順を仰ぎ見ることにもなるのです。「見よ、この人だ」とピラトが言ったときに人々の前に示されたイエス様の姿は、血でまみれた哀れな人間の姿でしたが、実際には私たちに救いをもたらす「神の子」であり、真の王でした。この逆説的なイメージこそが福音の真髄です。
最終的に、イエス様は世の拒絶と悪意に屈さず、喜んで十字架につけられることで真理を証しされます。その真理とは、「神は愛である」ということ、そしてその愛はこのように自分のすべてを犠牲にできるほどの愛であるということです。この愛のうちに入れられた者は、もはや死の奴隷ではなく、義と命の奴隷—すなわち神の子ども—となります。私たちがこの福音をもって生き伝えていくとき、世はなおも反発し嘲笑するかもしれません。しかし、それにもかかわらず十字架が持つ力は決して消え失せることがありません。
張ダビデ牧師がたびたび語ってきたように、「私たちが真理を握るとき、世のどんな力も神の愛から私たちを引き離すことはできない」のです。ピラトがイエス様を鞭打ち、大祭司たちが虚偽の証言を広め、群衆が「十字架につけろ」と叫んでも、結局イエス様は勝利されました。その勝利は世のやり方とは異なりますが、死の権威を打ち破る真の勝利です。そしてその勝利は、今も私たちと共にあります。私たちが十字架の前でへりくだってイエス様を王としてお迎えし、神の子である主に従順して歩むとき、その恵みと力が私たちの生き方を変え、私たちが属する共同体も新しくしていくのです。
結論として、ピラトの尋問過程(ヨハネ19:1-16)は、一人の人間の葛藤と政治的妥協に映し出された不正や、宗教的熱心という仮面に隠された致命的な悪を同時に照らし出すとともに、イエス様が罪人の救いのために栄光の玉座ではなく、恥辱の十字架を選ばれた壮大な決断を示しています。そしてこれらすべては「上から与えられていなかったなら、わたしに害を及ぼす権限はなかった」というイエス様のお言葉通り、神の主権のもとで起こった出来事なのです。私たちはこの御言葉を通じて、十字架が単なる不当な死ではなく、あらかじめ定められた贖いの出来事であったことを悟ります。また、私たちも日常生活の中で「十字架の道」をそれぞれの形で歩めるよう、神の御旨に従う信仰を求めるべきだと教えられます。
こうして二つの小主題に分けてヨハネ19章1節から16節を考察すると、張ダビデ牧師が語るように、真のクリスチャンのアイデンティティがどこに根ざすべきかが鮮明になります。すなわち、十字架の精神を通じて、高慢や暴力、偽りや偽善を捨て、人となられた神の愛に倣うことです。ピラトのように真理をつかむ力がなく世の声に屈したり、大祭司たちのように宗教的プライドゆえに真の真理を拒んだりしないように、日々自分を振り返り、悔い改めることが求められます。そして十字架で象徴されるイエス・キリストの死と復活を私たちの生の軸に据え、今日も聖なる従順と熱い愛をもって歩んでいくのです。
「見よ、あなたたちの王だ」というピラトの嘲り混じりの言葉が、信仰者の告白の見出しのように聞こえるアイロニー。そのアイロニーを通じて、私たちは「最も弱々しい姿をした神の子」が、実は「最も強大な救いの力」を持っていることを知ります。ゆえに、その道を選ぶことは決して敗北ではなく、新たな命と栄光へと至る近道です。聖書の数多くの証言がこれを裏付け、教会史における信仰の先人たちは命がけでこの告白を継承してきました。私たちがその道を喜んで歩むとき、神は私たち一人ひとりと教会を通して、ご自身の国と義を広げてくださることでしょう。
願わくは、ヨハネ19章1節から16節の御言葉に向き合う中で、ピラトやユダヤの指導者たちの姿に自分を重ねて悔い改める部分を見いだし、またイエス様が最後まで守り抜かれた十字架の従順に倣って、私たちの信仰告白が言葉だけでなく、生活によって証される成熟へと導かれることを望みます。張ダビデ牧師が説くように、真の福音とは私たちをキリストの十字架へと招き、自己否定の道を歩ませる力です。そしてその道の果てには、必ず復活の希望と命の冠が約束されています。これこそが、ピラトの法廷から始まった十字架の出来事が私たちに与える永遠の響きであり、教会共同体が世のただ中で証ししなければならない核心的な真理なのです。
www.davidjang.org